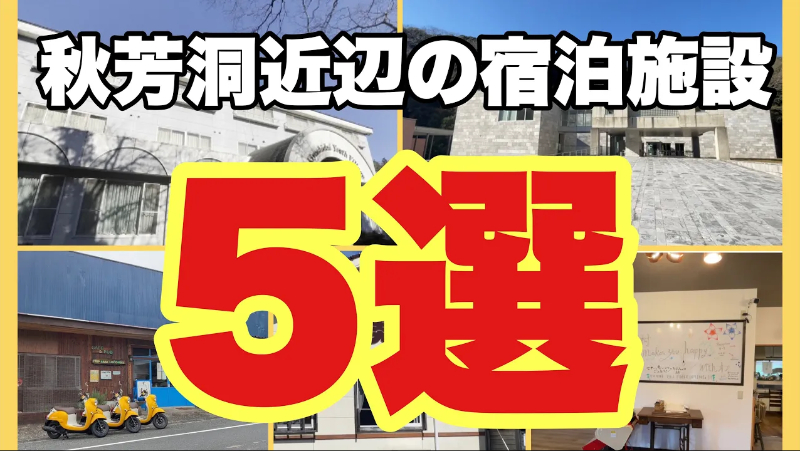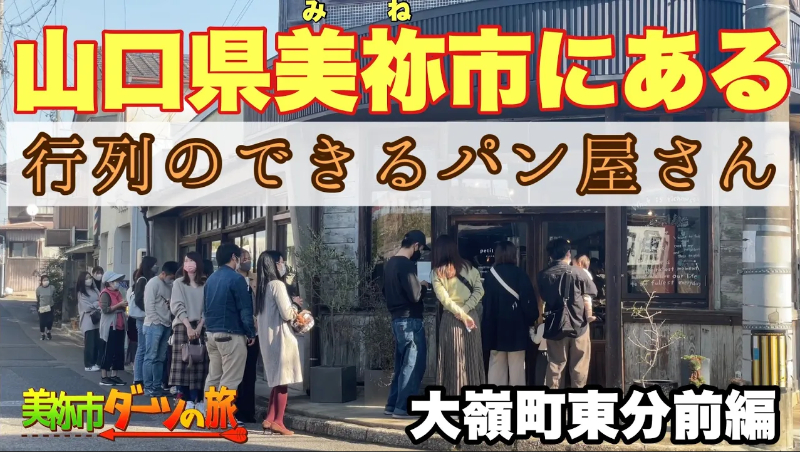特別天然記念物 秋芳洞(あきよしどう)
☞2024年ゴールデンウィーク期間中の秋芳洞営業時間等について
☞当日受付可能なガイドツアー実施中!「本日出発!秋芳洞ジオツアーについて」

秋吉台国定公園の地下100m、その南麓に開口する日本屈指の大鍾乳洞「秋芳洞(あきよしどう)」。
ひんやりと肌をさす冷気漂う杉木立を通り抜けると、秋芳洞の入口です。洞内の観光コースは約1km(総延長は11.2kmを超え国内第2位)、温度は四季を通じて17℃で一定し、夏涼しく冬は温かく、快適に観光できます。
時間が凍結したような不思議な自然の造形の数々は変化に富み、私たちの心に大きな感動を呼び起こさせてくれます。
☞お得に周遊!サファリランド&秋芳洞共通入場券について
秋吉台サファリランドと両方周遊される方にはお得な共通券がございます。両施設どちらか先の受付にて下記リンク先をスマートフォンで等で提示してください。※印刷も可
●秋芳洞/秋吉台自然動物公園サファリランド共通入場券について
☞3つの洞窟をお得に周遊!「秋吉台三洞物語」について
「秋芳洞・大正洞・景清洞」の3つの洞窟をお得な料金で入洞できる周遊共通チケットを販売しています。
秋芳洞(駐車場・バス停・トイレ・車椅子移動可能エリア)案内図
秋芳洞Youtube
| 所在地 | 山口県美祢市秋芳町秋吉3449番地1 |
| 入洞受付・閉洞時間 | 8:30~17:30 閉洞18:30 ※3月~11月 通常期 8:30~16:30 閉洞17:30 ※12月~2月 閑散期 ※黒谷入口 ・エレベーター入口からの入洞は16:30まで |
| 観光所要時間 | 目安:約60分(往復約90分) 秋吉台(カルスト展望台)へは、洞内途中のエレベーター口をご利用いただけます。 |
| 車椅子貸出 | 無料 秋吉台観光交流センター1階案内所にて受付(事前予約可能) ※事前に車椅子移動可能エリアをご確認ください。⇒ 秋芳洞(Akiyoshi-do)案内図 |
| 休業日 | 年中無休(年末年始も通常通り営業) |
| 交通アクセス | JR新山口駅からバスで約40分「秋芳洞」下車 中国自動車道「美祢東JCT」経由小郡萩道路「秋吉台IC」から車で5分 |
| 駐車場情報 | 正面入口付近 ・市営第1駐車場(200台) ・市営第2駐車場(300台) 1日1回利用 普通車500円 バイク無料(第1駐車場のみ) ※高さ2.5m迄の制限あり ・貸切バス駐車場(バス18台・無料) 黒谷入口付近 ・普通車120台、バス10台 ともに無料 エレベーター入口付近 ・普通車150台、バス2台 ともに無料 |
| 総合案内窓口 | 秋吉台観光交流センター総合案内所((一社)美祢市観光協会) TEL: 0837-62-0115 FAX:0837-62-0899 |
| 団体予約窓口 | 黒谷案内所 TEL: 0837-62-0103 FAX:0837-62-0323 観覧予約票:一般団体用(エクセル)・一般団体用(PDF) 修学旅行用(エクセル)・修学旅行用(PDF) |
| 障害者施設の団体様 |
申請書のご案内 手帳所持者の方が利用される施設、または団体様 お申込みの手順 1.下部より、手帳所持者証明書をダウンロードしてください。 【申請書のダウンロード】*印刷してご利用ください。 ご不明な点は黒谷案内所(TEL 0837-62-0103)までお問い合わせください。 |
| ジオガイド予約窓口 (団体) |
Mine秋吉台ジオパークセンター(カルスター) TEL: 0837-63-0040 予約期限:実施日の7日前まで 対応人数:ガイド1名につき原則10名まで(※要相談 最多20名まで) 集合場所:黒谷案内所 ガイド時間:1時間30分 料金:ガイド1名4,750円(入洞料別途要) ※ガイド手配が出来ない場合はお断りさせていただきます。 |
| 公共交通機関案内窓口 | 秋吉台観光交流センター 総合案内所((一社)美祢市観光協会) TEL: 0837-62-0115 FAX:0837-62-0899 |
※秋芳洞・秋吉台でのイベントや個人利用以外の撮影許可・申請に関しては「秋吉台科学博物館」ホームページをご確認の上、ご相談ください
秋吉台科学博物館HP TEL:0837-62-0640
入洞料金表 ※令和元年10月1日改正
| 個人 | |||
| 大 人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,050 | ¥700 |
| 団体 20名~99名 | |||
| 大 人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ¥1,100 | ¥900 | ¥800 | ¥550 |
| 団体 100名~199名 | |||
| 大 人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ¥1,050 | ¥800 | ¥750 | ¥450 |
団体 200名以上
| 大 人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ¥1,000 | ¥750 | ¥700 | ¥400 |
障害者手帳割引
| 個人 | |||
| 大 人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ¥650 | ¥650 | ¥525 | ¥350 |
| 団体 20名~99名 | |||
| 大 人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ¥550 | ¥450 | ¥400 | ¥275 |
| 団体 100名~199名 | |||
| 大 人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ¥525 | ¥400 | ¥375 | ¥225 |
団体 200名以上
| 大 人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ¥500 | ¥375 | ¥350 | ¥200 |
障害者手帳割引適用対象
※身体障害者手帳所持の方
所有者及び同伴者1名に適用。(種別を問わず)
※精神障害者手帳所持の方
所有者及び同伴者1名に適用。(等級を問わず)
※療育手帳所持の方
所有者及び同伴者1名に適用。(判定を問わず)
訪日外国人旅行者割引
| 団体 20名以上 | |||
| 大 人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 |
| ¥700 | ¥650 | ¥600 | ¥300 |
※代表者様は入洞チケット購入時にパスポートをご提示ください
マップ
JR新山口駅 → 秋芳洞
山口宇部空港 → 秋芳洞
角島大橋 → 秋芳洞
元乃隅神社(長門) → 秋芳洞
長門湯本温泉(長門) → 秋芳洞
湯田温泉(山口) → 秋芳洞
萩 → 秋芳洞
津和野 → 秋芳洞
下関 → 秋芳洞
錦帯橋(岩国) → 秋芳洞
関連記事